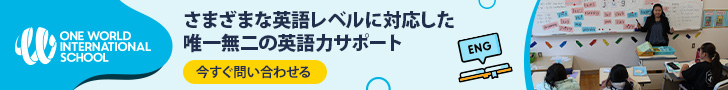小学校での英語教育が必修化され、保護者の中には「このままで本当に大丈夫?」「小学校の英語教育だけで足りているの?」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。
グローバル化が進む中で、どんな英語教育が良いか悩む人もいます。本記事では、日本の小学校における英語教育の現状と課題をわかりやすく解説し、インターナショナルスクールやバイリンガル教育との違いについても詳しく紹介します。お子さまに適した英語教育の理解にお役立てください。
小学校英語が必修化された理由とは?
日本の小学校では、英語教育がかつての「活動」から「教科」へと移行しました。それには英語力の重要性が世界的に高まっているという現状があります。
英語教育が小学校で必修化された背景にあるのは、国際化の加速です。グローバル社会では、英語がビジネスや学術、観光などあらゆる分野で必要とされており、日本国内でもその重要性が増しています。
2000年代以降、経済のグローバル化や人材の国際流動が進み、日本政府は子どもたちに「英語によるコミュニケーション能力」を早期から身に付けさせる必要があると判断しました。文部科学省は英語教育の段階的な導入を推進し、2020年には英語が小学5・6年生から正式に教科化されました。
このような取り組みはグローバル人材の育成と、早期から英語に親しませることで子どもの英語への苦手意識をなくす狙いがあります。英語が生活や将来の選択に直結する時代において、保護者が押さえておくべき重要なポイントともいえるでしょう。
2020年の学習指導要領改訂で変わったポイント
2020年度より、小学校における英語教育は大きく変わりました。それまでは「外国語活動」として5・6年生が年間35コマ、主に英語に慣れ親しむ活動を行っていましたが、学習指導要領の改訂により、英語が正式な「教科」として導入されました。
これに伴い、5・6年生は年間70コマの英語の授業を受けて、「聞く・話す」だけでなく「読む・書く」も含む4技能の習得を目指すことになります。さらに、3・4年生では外国語活動として、週1回程度の英語学習が実施されています。
この背景には、国際社会で活躍できる人材の育成という文部科学省の意図があります。将来的に英語が単なる「教科」ではなく、日常的に使える「道具」となるように、子どものうちから英語に触れる環境を整えることが狙いです。
これまでとの大きな違いは、英語が教科になったため評価対象になることです。以前は「体験活動」程度だった英語が、成績として評価される教科に格上げされたことで、教育現場の取り組みや子どもたちの意識も大きく変わりました。これにより、より体系的な英語学習が求められています。
主な改訂ポイントには以下のようなものがあります。
学年 | 教科名 | 学習時間 | 内容の変化 |
小学3・4年 | 外国語活動 | 年間35コマ | 音声中心で「聞く・話す」に重点 |
小学5・6年 | 英語(教科) | 年間70コマ | 「読む・書く」も含まれる |
文法の理解も必要ですが、コミュニケーション重視の内容となっており、「英語を使ってやりとりする力」を育てることが目的です。
グローバル時代に求められる英語力とは

現代社会は、単に「英語が話せる」だけでは通用しない時代に突入しています。以前は、受験英語や読み書き中心のスキルが重視されていましたが、グローバル化が進む現在、求められる英語力はより実践的で、かつ多様な場面に対応できる「使える英語」へと変化しています。
例えば、国際会議での議論や多国籍チームでのプロジェクト協働、さらには異文化理解を伴うコミュニケーション能力などが必要とされているのです。
日本の子どもたちにとっても例外ではなく、将来のキャリアにおいて英語力は大きなアドバンテージとなります。そのため、早期の段階から英語に慣れ親しみ、「英語で考える」「英語で自分の意見を伝える」スキルを育てることが求められます。
英語は「試験のための知識」ではなく、「世界とつながるための言語ツール」なのです。そのため、以下のような力が小学生のうちから育成されることが理想とされています。
- 聞く力と話す力のバランスが取れた英語力
- 自分の考えを英語で表現できる力
- 異文化を理解し尊重する姿勢
文部科学省は、英語教育で育成する「資質・能力」を、「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱としてまとめています。単語や文法を覚えるだけではなく、相手の文化や価値観を理解しながら、伝え合う力を育てることがポイントです。
英語を「知識として学ぶ」だけでなく、「ツールとして活用できるようになること」が重要といえます。これは将来、国際的な環境で活躍する際の土台にもなるでしょう。
日本の小学校英語教育の現状と課題

英語が教科として導入され数年が経過しましたが、現場ではさまざまな課題も浮き彫りになっています。
小学校で英語が必修化されたことで、子どもたちが早期に英語に触れる環境は整いつつあります。しかし、授業時間の短さや指導体制のばらつきなど、多くの課題も残っています。
学校ごとの取り組みに差がある他、教員の英語力や専門性にも限界があり、効果的な英語教育の実現には至っていないのが現状です。英語を学ぶ機会がある一方で、「使える力」につなげるための環境整備が求められています。
保護者が不安に感じる点も少なくありません。ここでは、今の小学校英語教育の「実態」と「足りない部分」について詳しく見ていきます。
授業時間が少ない? 小学校の英語学習の実態
小学校での英語教育は制度上「必修化」されたものの、実際の授業時間数はまだまだ十分とはいえません。
2020年の学習指導要領改訂により、5・6年生では英語が「教科」となり、年間70コマ、週あたり2コマ程度の英語授業が設けられました。一方、3・4年生は年間35コマ(週1回)の「外国語活動」にとどまっており、英語に触れる機会は限定的です。
また、カリキュラムの制約や教員の負担もあり、他教科と比べて英語に割けるリソースが少ないのが現状です。さらに、教科化された5・6年生でも、教員の専門性や指導力にはばらつきがあります。
専任の英語教師がいる学校がある一方、多くは英語専任の教員が配置されておらず、担任の先生が授業を行うケースが多く見られます。特に英語の発音や表現方法に自信がない先生の場合、授業が教科書の読み合わせで終わってしまうこともあるでしょう。
そのため、英語教育の到達度にも地域差や学校間格差が生じており、子どもによって「英語に親しめたかどうか」に大きな差が出ています。英語を苦手と感じたまま中学に進学すると、英語への苦手意識が固定化されてしまうこともあります。
このように発音や指導法に対する不安の声も少なくありません。質の高い英語教育を全校一律で実施するには課題が残っています。公立小学校において、英語を「使える言語」として定着させる教育を行うには、まだ改善すべき点が多くあるといえます。
「聞く・話す」は増えたけど、アウトプットの機会が不足?
学習指導要領の改訂により、小学校の英語教育においては、「聞く」「話す」活動が増えたことは確かです。特に中学年では、英語に親しむことを重視し、ALT(外国語指導助手)などと一緒に英語の歌やゲームを通じて学ぶスタイルも多くなってきました。
しかし、簡単なフレーズのリスニングやスピーキングは増えましたが、英語を使って自発的に表現する機会はまだまだ少ないといえます。子どもたちが英語で自由に発言したり、対話を重ね「英語を使って自分の気持ちを伝える」といったアウトプットは不足しているのが現状です。
その背景には、授業時間の短さやクラスの人数規模、さらには教員の指導経験不足など、複数の要因があります。英語を聞いて理解することはできても、実際に口に出して使う経験が少ないため、英語が身に付く実感を得にくいのが実情です。
特に、以下のような課題が指摘されています。
- 英語で会話する時間が圧倒的に少ない
- 発音や表現に間違いがあっても、訂正やフィードバックが少ない
- クラス全体で一斉に行う授業では、個別の成長に対応しきれない
子どもが英語を使う経験が少ないことで、「英語を話すのが恥ずかしい」「間違えたら嫌だ」といった消極的な態度につながるケースもあります。
英語力の定着には、受け身の学習だけでなく、自ら発信する機会が不可欠です。例えば、自分の考えを英語で発表する「Show and Tell」や、簡単なスピーチ活動などを取り入れると、英語を使う力を養うことができます。
学校だけで補いきれない部分は、家庭や地域、民間の英語教室などを利用して、子どもたちが「英語を使ってみる」経験を積むことが大切です。英語は練習を通じて使える力が育ちます。授業内外でのアウトプットの機会を確保することが、英語力の向上には欠かせません。
英語力を伸ばすために必要な環境とは

小学校での英語教育だけでは、十分な英語力を習得するのが難しいと感じる保護者も多いでしょう。その場合、家庭でのフォローや外部の教育機関の活用がカギとなります。
ここでは、入学前から始められる準備や家庭でできるサポート、さらに英語教室・プリスクールの役割について詳しく紹介します。
入学前にできる英語の準備とは?
小学校での英語教育が始まる前に、どのような準備をすれば良いのか不安に思う保護者の方も多いでしょう。小学校に入る前の幼児期は、言語習得にとても適した時期です。この段階で英語に触れる機会を持つことは、耳の良さや発音の習得において大きなメリットがあります。
英語における早期教育では必ずしも「読み書き」を教える必要はありません。むしろ、英語に対してポジティブな印象を持ち、「聞く・話す」ことに対する抵抗感をなくすことが、最も重要な準備といえます。
例えば、英語の絵本を読み聞かせる、英語の歌やアニメを日常的に流すといった方法は、自然な形で英語の音に慣れるのに良いでしょう。英語特有のリズムやイントネーションに触れれば、発音やリスニング力の土台を作ることができます。
親が英語を流暢に話せなくても構いません。「間違えても大丈夫」という環境の中で、「英語って楽しいね」と一緒に感じる親の姿勢が、子どもに安心感を与えます。
さらに、英語で簡単なあいさつや自己紹介など、生活に身近な表現を一緒に練習するのもおすすめです。ポイントは、「正しく話すこと」よりも「英語を使ってみること」に重点を置くことです。
入学前にできる具体的な準備には次のようなものがあります。
- 英語の絵本の読み聞かせ
リズム感や音のパターンを楽しむことで、自然と英語に親しめる
- 英語のアニメや番組を視聴する
ネイティブの発音に触れる機会を増やすことができ、英語の音に耳が慣れる
- 親子で簡単な英語フレーズを使う
日常生活の中で「Thank you」「Here you are」など、シンプルな表現を繰り返すことで、英語が生活の一部になる
このような自然な形でのインプットは、子どもにとって「英語=学習」ではなく「英語=楽しい」という意識を育てるきっかけになります。
入学前に英語の基礎を固めようと無理に詰め込むのではなく、自然な興味と好奇心を引き出すことが、将来の英語力につながっていくのです。英語を生活の一部として楽しむ習慣作りが大切です。
小学校入学後、家庭でできるフォロー
小学校で英語活動や授業が始まっても、限られた時間の中で十分な言語習得を期待するのは難しいといえます。
そこで重要になるのが、家庭でのフォローです。家庭は、子どもがリラックスした環境の中で、英語に触れたり話したりできる貴重な場です。学校で学んだ英語を家庭で繰り返し使うことで、習った内容が定着しやすくなります。
「今日はどんな英語を習ったの?」「どんなことが楽しかった?」と問いかけると、学校での学びを自然にアウトプットする機会になります。言葉にすることで記憶に残りやすくなるでしょう。
また、日常会話の中で簡単な英単語を取り入れる、英語の絵本を一緒に読む、英語の動画を一緒に楽しむなども良いでしょう。内容を一緒に楽しみながら「これは英語で何て言うのかな?」と親子で探求する姿勢を持つと、子どもの好奇心を刺激し、英語に対する関心も高まります。
また、間違いを指摘するよりも「使ってみたね、えらいね」と努力を認める声かけが、学びの意欲を引き出します。学習の進捗を一緒に振り返る時間を作るのも効果的です。
英語教育は、家庭と学校の二本柱で進めていくのが理想です。家庭でのサポートは、知識の補完よりも「英語を使える」「英語は楽しい」と思える感覚を育む場と考えると良いでしょう。小さな積み重ねが、将来の英語力の向上につながります。
英語教室やプリスクールは必要?
小学校の英語教育だけで本当に足りるのかと不安に感じ、幼少期から英語教室やプリスクールの利用を検討する保護者も少なくありません。
必ずしも全員に必要というわけではありませんが、「英語を自然に使う環境を整えたい」「より深く学ばせたい」と考える家庭にとっては、有効な選択肢となります。
英語教室では、歌やゲームを取り入れながら「英語を楽しく学ぶ」スタイルが一般的で、学習に対する抵抗感を抱かせずに英語力を高められるのが魅力です。また、少人数制やネイティブ講師による指導により、学校よりも発話量を確保しやすく、アウトプットの練習にもなります。
一方、プリスクール(英語保育園)は、生活全体が英語環境であることが特徴です。遊び、会話、食事といった日常活動全てが英語で行われるため、自然と英語に慣れ、言語習得がスムーズに進みます。
一般的には英語を母国語としているネイティブ講師が在籍しています。英語の習得にはネイティブと日常生活を過ごすことも重要です。
いずれの方法を選ぶにしても、大切なのは「子どもが楽しめるかどうか」です。無理なく継続できる環境を選び、家庭でも子どもが英語に関心を持ち続けられるような工夫をしていくことが、最終的に英語力の伸びにつながっていきます。
以下にそれぞれの特徴をまとめます。
種類 | 特徴 | 向いている家庭 |
英語教室 | 会話重視でフォニックスも 週1~2回程度の通学型 | 学校の学習を補いたい、費用を抑えたい家庭 |
プリスクール | ネイティブと過ごす生活型 長時間の英語環境 | 小さいうちから英語に浸らせたい家庭 |
どちらを選ぶにしても、「英語を使う環境」が整っているかを確認することが大切です。特にプリスクールでは、カリキュラムや先生の質の差が大きいため、見学や体験を通じて慎重に判断することが重要です。
インターナショナルスクールの英語教育との違い

インターナショナルスクールでは、英語が「外国語」ではなく「共通言語」として日常的に使われています。そのため、公立小学校の英語教育とは根本的にアプローチが異なります。
ここでは、以下の二つのポイントについて詳しく解説します。
- 英語を「教科」として学ぶのではなく、「言語」として使う環境
- 英語だけでなく、多文化理解やグローバル思考も育む
英語を「教科」として学ぶのではなく、「言語」として使う環境
公立小学校では、英語は教科の一つとして位置づけられ、授業時間も限られています。それに対し、インターナショナルスクールでは英語が日常のコミュニケーション手段として使われています。
例えば、算数や理科、美術などの教科も全て英語で行われるため、子どもたちは自然と「英語で考え、英語で表現する」能力を身に付けていきます。
英語が言語として日常的に使われるため、学習ではなく「体得」に近い形で英語力が育まれていきます。また、単語の暗記や文法問題に偏ることなく、実際の文脈の中で英語を理解・活用できるようになるのが特徴です。
さらに、英語を「使うこと」が当たり前の環境にいるため、発音やイントネーションも自然とネイティブに近づきます。教科書ベースの学習だけでは習得しにくい、柔軟で臨機応変な表現力も養われるのです。
こうした力は、単に英語ができるという範囲を超え、将来の留学や国際的な仕事にも直結する「実用的な英語力」として大きな強みになります。この違いが子どもたちの英語力に多大な影響を与えます。
方針 | 公立小学校 | インターナショナルスクール |
英語の扱い | 教科(週数回) | 言語(毎日使用) |
学び方 | 学習指導要領に沿った基礎学習 | 英語で全ての教科を学習(算数や理科も英語) |
英語使用の頻度 | 限定的 | 常時(校内での会話や活動全て) |
このように、インターナショナルスクールでは「英語を学ぶ」のではなく「英語で学ぶ」という点が大きなポイントです。おのずから英語が身に付く環境が整っているといえます。
英語だけでなく、多文化理解やグローバル思考も育む
インターナショナルスクールの大きな特長の一つが、英語教育を軸にしながら「多文化理解」や「グローバル思考」を育むカリキュラムが組み込まれている点です。
子どもたちは日常的に異なる国籍や文化的背景を持つ友人や教師と接しながら学ぶため、自分とは異なる価値観や考え方を受け入れる力が自然に養われます。
このような多様性に触れる環境だと「正解は一つではない」という柔軟な思考を持ちやすく、他者を尊重しながら自分の意見を発信する力が培われていきます。英語力が高まるだけではなく、グローバルな視点が養われるのも、インターナショナルスクールの教育の大きな魅力です。
また、多文化共生を前提としたプロジェクト型学習やディスカッション、異文化イベントなどを通して、子どもたちは他国の伝統や宗教、歴史について学びます。それにより、相手の立場に立って考える力やコミュニケーション力が身に付いていきます。
バイリンガル教育のメリットとは?

バイリンガル教育とは、二つ以上の言語を使って教育を行い、どちらの言葉も自然に使える状態にすることを目指す教育法です。
幼少期から始めると、言語だけでなく思考力や柔軟性も育めるといわれています。ここからは、バイリンガル教育が子どもに与える具体的なメリットを解説します。
幼少期の英語学習が発音やリスニング力に与える影響
幼少期は音の感覚が非常に鋭く、ネイティブに近い発音やリズムを習得しやすい時期です。この期間に英語に触れると、日本語にはない音の聞き分けや、英語特有のイントネーションを無理なく吸収できます。
特に幼少期の間に英語に触れると、以下のような効果が期待できます。
- 発音が日本語訛りになりにくい
- リスニング能力が高くなる
- 音のバリエーションに慣れるため、語学への抵抗が少なくなる
このように、早期にバイリンガル教育を受けると「音の壁」を越える能力が育ちやすくなります。ただし、強制されるのではなく「楽しい」という感覚の中で学ぶことが成功の鍵です。
発音・リスニング力だけじゃない! バイリンガルの強み
バイリンガル教育の魅力は発音やリスニングだけにとどまりません。複数の言語を使い分けることで、認知力や情報処理能力も高まるという研究結果もあります。
具体的なメリットとしては以下のようなものがあります。
- 集中力と注意力が鍛えられる
- 言語の構造理解が深まり、国語力や論理的思考にも好影響
- 異なる文化や価値観を柔軟に受け入れる力が育つ
また、バイリンガルの子どもは「状況ごとにそれぞれの言語で考える」傾向があり、母語と英語の両方の言葉の力が高くなったり、さまざまな観点から考えられるようになったりするケースもあります。単に二つの言語を話せること以上に論理的思考力や問題解決能力が高まり、学習の柔軟性が身に付くのです。
未来のキャリアへの可能性
グローバル化が進む現代において、バイリンガルであることは大きな資産となります。将来的に海外の大学への進学、外資系企業での勤務、国際的なプロジェクトへの参画など、進路の可能性が大きく広がります。
バイリンガルが海外の大学への進学やキャリア形成で有利になるポイントは以下の通りです。
- TOEFLやIELTSなど英語能力の証明試験に強い
- 英語面接や英語での資料作成にも抵抗がない
- 通訳、翻訳、国際機関、航空業界などで需要が高い
さらに、英語を使って学んだ経験があると、「英語で考える」ことができるため、単なる語学力にとどまらないグローバルな視点を持つ人材として評価されます。子どもの可能性を広げるために、バイリンガル教育を行うことは非常に価値があるといえます。
インターナショナルスクールを選ぶポイント
インターナショナルスクールは英語環境とグローバル教育を子どもに提供する魅力的な選択肢ですが、その質や教育方針は学校によって大きく異なります。
子どもにとって最適な学びの場を選ぶためには、カリキュラムの内容、教師の質、そして保護者がチェックすべきポイントをしっかり理解する必要があります。この章では、学校選びに欠かせないポイントを具体的に紹介します。
カリキュラムの違い(IB、ケンブリッジ、アメリカ式など)
インターナショナルスクールの教育カリキュラムにはさまざまな種類があり、それぞれの特色や教育指針があります。以下に代表的なカリキュラムの概要をまとめます。
カリキュラム | 特徴 | 向いていると思われるタイプ |
IB(国際バカロレア) | 探究型学習とプレゼン力重視 | 自主性があり、多角的に物事を考えられるタイプ |
ケンブリッジ | 決まったカリキュラムがあり、目標達成が重視される | アカデミックに強く、論理的に考えられるタイプ |
アメリカ式 | 芸術や体育のクラス、課外活動等が提供される 個性重視で、柔軟な教育が魅力 | 独立心があり、自分のペースで学びたいタイプ |
カリキュラムによって、学び方や評価基準、進学先の選択肢などにも影響が出ます。子どもの個性や将来の方向性を考慮し、合ったプログラムを選ぶことが大切です。
先生の質や教育方針はどうやって見極める?
インターナショナルスクールの質は、教師のレベルと学校の教育方針によって大きく左右されます。見学時には以下のようなポイントを確認すると良いでしょう。
- 教員の資格や国籍、教育経験
IBやケンブリッジのカリキュラムでは、専門のトレーニングを受けた教員がいるか
- 授業の進め方や子どもへの接し方
子どもの主体性を引き出す授業が行われているか、言語サポートがあるか
- 教育理念と家庭の価値観の一致
学校が大切にしている価値や学びのスタンスが、家庭の教育方針と合致しているか
実際の授業を見学したり、在校生の保護者に話を聞いたりすることで、見えにくい部分もしっかり把握できます。
保護者が気をつけるべきポイントとは?
インターナショナルスクールへの進学には、英語教育の内容以外にも検討すべき部分が多くあります。後悔しない選択をするために、以下のような点をチェックしておきましょう。
- 学費や追加費用の確認
授業料の他に教材費やスクールバス代、イベント費などが加わることがある
- 家庭でのフォローアップが可能か
学校だけでなく家庭でも英語に触れる機会を作ることが大切
- 進路の確認
中学や高校への進学があるか、外部への進学実績があるかも大切な判断材料
また、保護者自身も学校行事や英語でのイベントに関わる場面があるため、学校関係者とも前向きにコミュニケーションを取ることが求められます。
小学校の英語教育ならインターナショナルスクールOWIS
日本国内でバイリンガル教育や国際的な学びを希望する保護者にとって、OWIS(One World International School)は選択肢の一つです。シンガポール発のグローバルスクールであるOWISは、日本でもその理念と教育内容を取り入れたカリキュラムを実施し、質の高い英語環境と国際的な教育を提供しています。
OWISの最大の魅力は、「英語を学ぶ」のではなく、「英語で学ぶ」環境が整っている点です。それにより、子どもたちは自然に英語を使いこなす力を体得するだけでなく、多文化の中で協調性や自己表現力も磨いていきます。
OWISの特長を以下にまとめました。
特長 | 内容 |
英語環境 | 日々の授業が全て英語で行われ、生活の中で自然に英語が身に付く |
講師 | IB(国際バカロレア)資格を持つ講師陣が指導 |
カリキュラム | IB(国際バカロレア)認定教育を実施 |
多様性コミュニティ | 世界各国から集まった教師や生徒と交流でき、異文化理解が深まる |
学費 | 他のインターナショナルスクールと比較して学費が抑えられており、継続的に通いやすい |
また、OWISでは「子どもを中心に据えた教育」を重視し、一人一人の成長に合わせた丁寧な指導が行われています。 英語力だけでなく、自分の意見を伝える力や考える力を伸ばすカリキュラムです。「英語が話せる」だけでなく、思考力や柔軟性などの面でも学びを得られます。
未来につながる英語教育を選ぼう –「学ぶ英語」から「使う英語」へ

これからの時代、英語は「学力」や「受験対策」のためだけでなく、世界とつながるためのコミュニケーションツールとしての役割がより大きくになってきます。小学校の英語教育が進化しているとはいえ、グローバル社会で必要とされる本質的な英語力を育てるには、より深い学びと実践が求められます。
この記事で紹介してきたように、公立小学校の英語のカリキュラムには限界があり、補完的な家庭学習や英語教室が必要でしょう。
英語力を高めグローバルな人材を目指すなら、インターナショナルスクールやバイリンガル教育のような他の選択肢の検討が必要になってきます。特に、「英語で学び、考える力を養う環境」が今後の英語教育には不可欠といえます。
「インターナショナルスクールOWIS大阪」では英語教育にふさわしい環境が整っています。お子さまの英語教育を検討している保護者の方は、ぜひ以下のページをチェックしてみてください。
お子さまの個性や将来の目標に合わせて、小学校の英語教育を選びましょう。英語を「学ぶ」から「使う」へと進化させることが、未来を生き抜く力を育てる第一歩になります。
実際に、「OWIS大阪を見てみたい」という人には、学校見学やオープンキャンパスもおすすめです。それぞれのリンクからチェックしてみてください。